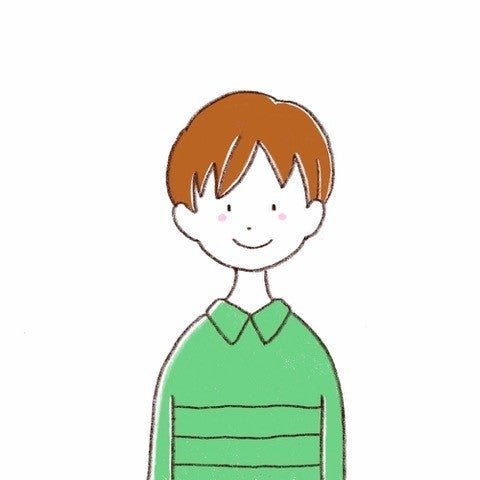小・中#13-1: It’s “Save the Koala Day!” 「コアラの日です」(前)
小学校高学年では、今年度から教科になった「外国語」の学習を通して、児童は600~700語の英単語に触れることになっています。
まだ英語学習が始まって間もない時期に、こんなにたくさんの単語をどうやって導入するのだろう・・・と心配される方がおられるかもしれません。ですが、英語学習を始めた直後は、目の前にある「もの」を英語で表せることが楽しくてたまらない段階。そして、小学校高学年特有の興味・関心に沿って、児童には「英語で何と言うのか知りたいもの」がたくさんあるのです。
中学校英語教育を経験されたことのある先生が、小学校の授業を体験して、「小学生が、中学校では扱わないような英単語をよく知っていることに驚いた」というお話をされているのを何度か聞いたことがあります。
例えば、「昆虫」を insects でまとめてしまうのは小学校では難しいもの。つまり「カブトムシ」、「クワガタ」、「バッタ」、さらに「おんぶバッタ」も言ってみたい。もちろん「おんぶバッタ」を “Atractomorpha lata” という専門用語で覚えるわけではありません。指導者が発音してみせたり、コンピュータの発音を聞いたりする経験が貴重なのです。何度か繰り返して言おうと試みる児童もいますが、そのうち「難しいなぁ」と。
さらに「色」を表す単語を、有名な “Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?” の絵本を読み聞かせしながら紹介すると、「青い馬」は “A blue horse.” では終わりません。どこで覚えたのか、「light blueだよ!」、「dark blueだよ!」、「それは blue じゃないよ。black blue だよ!」(”blue-black” のことか?新色か?)などという声が上がり始めます。子どもの感性の豊かさを感じる一幕です。このように、1つの単語から、児童の世界はどんどん広がります。
また前置きが長くなりました ・・・ 。
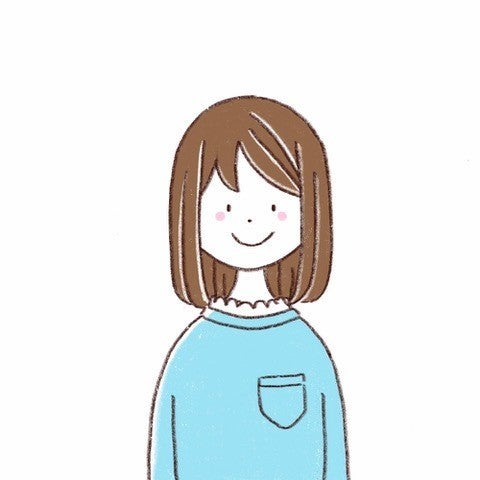
動物について話をしよう!
さて、児童の多くは動物が大好き。
まるで動物博士のように、様々な動物の名前を知っている児童もいます。だから「英語で動物の名前をどう言うか」を学ぶと盛り上がります。
今回はこの「動物」を大テーマに、Small Talk の展開を考えてみたいと思います。
「動物について話をしよう」と思った時、どのように児童とのやり取りを始めることができるでしょうか。
いつものように、既習表現を考慮して指導者がまず自分のことを話すとすれば、このような内容を表すことができます。
T: I like animals. (Especially,) I like dogs. I have a dog. [His name is Pochi.] (He is) five years old. I walk Pochi every morning. I like Pochi very much. [He is cute and clever.] He can catch a ball. But he can’t do “mate.” Last summer, my family went to the sea with Pochi. We enjoyed walking along the beach. I want to go to the mountain with Pochi next summer.
ここでは敢えて、所有格の代名詞 him を用いずに話しています。何度もPochiで置き換えていますが、思い切って him を入れて伝えたとしても、写真を指差したり、ジェスチャーを取り入れたりしながら話せば、内容は児童に伝わると思われます。
ただし「him は所有格の代名詞で、『彼の』つまり『ポチの』という意味です」という説明は小学校段階では必要ありませんし、児童が話を楽しく聞いているようであれば、him という語については触れません。
これに続く児童への問いかけとしては、以下のようなものが考えられます。
① (I like animals.) Do you like animals?
② (I like dogs.) Do you like dogs?
「好きかどうか」に偏ってしまいましたが、これには訳があります。最初の問いは「幅を広く」とっておくということです。
③ (I have a dog.) Do you have a pet?
例えば上の③の問いは、“Do you have ~?” (~を飼っていますか?)という表現(の定着)に焦点を当てたやり取りであれば可能と思われます。しかし、せっかく「動物」という大きなカテゴリーでテーマを設定していることを考えれば、最初から指導者の側で「家でペットを飼っているかどうか」という狭い話題になっていると感じます。
できれば児童がテーマ(ここでは「動物」)について、自分が伝えたいことに向けてやり取りを発展させる自由度を高めた状態で最初の問いを設定することも、活動の目的によっては重要です。
では上の2つの問いかけに続いて、どのような展開が起こり得るかを考えていきます。
◆”Do you like animals?” で始める
指導者が自分のことを伝えた後で、児童に問いかけます。この時、YES という肯定の反応があれば、”What animal do you like?” と続けて動物の種類を掘り下げていきます。
T: Do you like animals, S1?
S1: Yes.
T: Oh, you like animals. Me too. I like dogs. What animal do you like?
S1: I like … キリン.
T: You mean, giraffes? Yellow and black patches. Very tall?
S1: Yes.
T: You like giraffes! (They are) popular in a zoo.
一方、
S1: No. I don’t like animals.
という否定の反応があった場合、どう続けるとよいでしょうか。実際の授業において、指導者と児童、あるいは児童同士の対話でよく見かけるのは、
T: Oh.
だけで(何を続けようかと悩んで)沈黙してしまう姿。あるいは
T: Oh, you don’t like animals.
だけ。
「(S1さんは)動物が嫌い(苦手)なんですね」と言われたら、母語であれば「はい、そうなんです。実は・・・」と返答できそうですが、”Do you like animals?” という英語の問いに、何とか頑張って事実を伝えることができた児童もいると思うのです。そうした児童は “Oh, you don’t like animals.” と言われたら、どう反応することができるのか・・・と考えてしまいます。
さらに、
T: (Oh, … ) why?
とだけ、即座に聞き返す例もありました。これまでも述べてきましたが、やり取りの相手のことばに対して、何でもかんでもすぐに「なぜ?」と尋ねるのではなく、児童には、やり取りの内容を深く考えて反応できる力を育てたいと思います。
難しく考える必要はありません。上の反応を結びつけて反応してはどうでしょうか。
すなわち “I don’t like animals.” と、しっかり自分のことを伝えた児童のことばを「まず」指導者として、しっかりと受けとめます。それから「その理由を教えてよ」と促すことが大切だと思うのです。
T: You don’t like animals. (「○○さんは、動物が嫌いだったんだね。(今知ったよ。)」のように理解を示しながら児童の発言を繰り返した後で) Why?
であれば、児童も「話したことが先生に伝わった」と自信をもてますし、その後の答えにおいても「どうして自分は動物が嫌い(苦手)だったのかな」と素直に理由を考えることができます。
小さなことですが、こうした配慮も、指導者が児童にモデルとして示すことのできる相手意識をもった反応のしかたと言えるのではないでしょうか。
◆ “Do you like dogs?” で始める
もうひとつの問いから始める展開例です。
T: Do you like dogs, S2?
S2: Yes.
T: Oh, you like dogs too. Me too. What kind of dogs do you like?
上の例も、「犬が好き」という YES の返答を掘り下げて、「どんな犬が好きか」をさらに尋ねています。さらに NO の場合も、
T: Do you like dogs, S2?
S2: No.
T: You don’t like dogs. Then, what animals do you like?
このように、「犬」という「動物の種類のひとつ」から「動物」というカテゴリー全体に話を戻して問いを続けることができます。ただし、S2 がそもそも「動物が好きではない」という可能性があるので、2つ目の問いの前に “Do you like animals?” と尋ねてもよいかもしれません。
このように、「どういう問い(疑問文)をするか」、「児童の返答に対してどのように反応するか」は、やり取りの「ねらい」(どういう力を伸ばすのか)に応じて、十分に検討されていなければなりません。児童のことばをしっかりと聞き、ゆっくりで良いので、意味ある反応を丁寧に心がけていくことが大切です。
***********************
ここまで「動物」を大きなテーマに Small Talk のはじめの部分だけを考えてきました。実はまだ今回のタイトルにある “Save the Koala Day” のことも、「コアラ」という動物も出てきていません。
次回、特定の動物に焦点を当てた展開まで進めてみたいと思います。