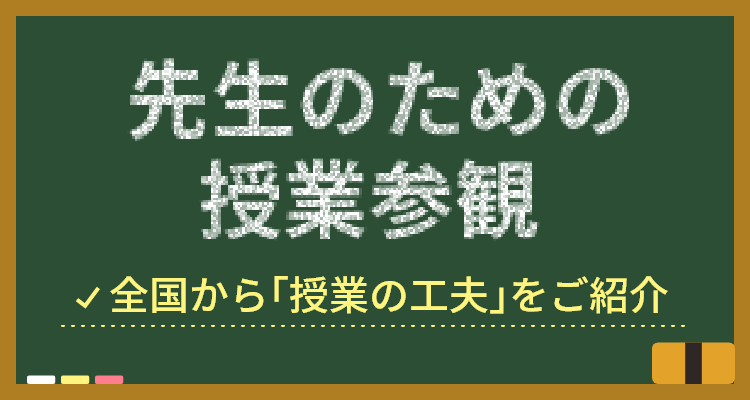【第16弾】実践紹介『小学校「外国語」の授業で大切にしていること』
東京都三鷹中央学園三鷹市立第七小学校
主任教諭 今西 佑 先生(6年担任)

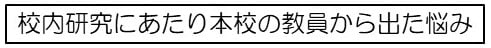

・教員が英語力に自信がないのに、「聞く」⇒「話す」の授業をどう展開すればいいの?
・そもそも児童の聞く姿勢を育てるには?また、児童が自分から話したくなるようにさせるにはどうしたら
いいの?
・中学校までにアルファベットはどう定着させる?
このような悩みが上がりました。きっと同じように悩んでいらっしゃる方はいるのではないかと思います。そこで、本校の外国語の授業で特に大切にしていることを以下3つにまとめ、ご紹介します。
1. まずは指導者が自分のことを話そう!
「聞く」⇒「話す」⇒「読む」⇒「書く」の流れを大切にし、繰り返し聞かせることを意識しています。担任はすべてを英語で話そうとするのではなく、児童の実態に合った言語材料を明確にし、何をインプットさせたいかを意識し授業を行うようにしています。Unit 6 This is my town.では、We have~. You can~.の表現を繰り返し使うことを意識しながら、担任が自分の出身地の町を紹介したり、学校がある地域でよく行くお店を紹介したりするなど、まずは指導者が「自分のこと」を話すことで児童も聞く意欲がぐっと高まります。その際「あの言葉は英語で何て言うのかな?」と悩むことがあると思います。しかし、その時間にインプットさせたい言語材料以外は無理して英語で話す必要はありません。英語力に自信がない教員も、自分のことを決められた言語材料で話し、無理なく「聞く」→「話す」の授業を展開することを校内で大切にしています。
2. 子供たちが聞きたくなる・話したくなる発問の工夫
Unit 6 This is my town.では、「三鷹の良さを伝えよう!」という最終目標を、国語科と関連し設定しました。(外国語はALTに対して、国語は地域に発信)しかし、毎時間、児童に住んでいる町について話させるのは、聞く方も話す方も飽きるので、意欲がどんどん低下していきます。そこでWe have~. You can~.などの言語材料を定着させるため、様々なバリエーションの発問でやり取りを行いました。目的・場面・状況を明確にし、子供の自由な発想を大事にすることで児童の「聞こう・話そう」とする姿の高まりが見られるようになりました。
例「100年後の三鷹にあるもの」「夢の教室にある物を紹介しよう」など
発問を工夫することで、友達の発言を聞く意識がより高まるので、指導者は児童一人一人に答えさせ、言語材料をしっかり言えているかを確実に見取ることもできます。
また4年生Let’s Try! 2 What do you want? の単元でも同様に、考えたピザやパフェを紹介し続けるのでなく、児童が「wantで色んなことを伝えられる!」と実感させられるかどうかを意識し、授業を展開していきます。
例「ドラえもんに何をお願いしたい?」「○○先生の誕生日プレゼントを買うなら?」
「来月の遠足のお弁当、何入れて欲しい?」「特性野菜ジュース作るなら?」
ただ覚えたことを「A→B→A→B」と言い合うのはコミュニケーションではないので、活動前に指導者が話し方を示しすぎないということも重要だと考えます。大切なのは『子供がどのような内容を、どのように話しているか?』ということです。さらに中学年でも高学年でも相手意識をもちながら、「相手に伝わるようにどのような工夫をしているか?」あるいは「どのような既習表現を使って伝えているか?」を日々の授業で見取っていくことの大切さを校内で共有しています。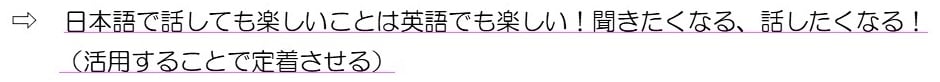
3. アルファベットの定着は日々の積み重ね
本校では、4~6年生の授業の始め5分間を使ってアルファベットタイムを設定しています。中学年はアルファベット遊び、5年生は読みとなぞり書き、6年生はアルファベットをランダムに書くことを中心に行っています。日頃からの積み重ねがあるので、6年生の1学期終了時には97%の児童が小文字をすべて書くことができていました。高学年はワードブックを活用しながら、たくさんの語彙に触れる時間も作っています。指導のポイントとしては、①中学年は、児童が自分からアルファベットの名称を言いたくなるような活動を展開すること、②高学年は、児童の実態に合わせ少しずつアルファベット定着のステップアップを図ること、を校内で意識して取り組んでいます。
3・4年生:アルファベット探し・アルファベット体操・触ると痛そうなアルファベットは?
アルファベットジグザグ歌い・大文字と小文字のマッチングゲーム・・・など
5年生:アルファベットの名称と音・四線の指導・なぞり書き
6年生:ランダムで言われたアルファベットに○を付ける→四線上に書く ・・・など