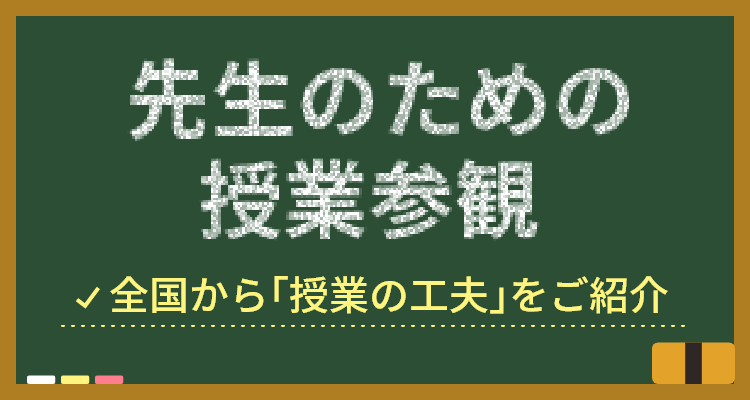【第23弾】新教科書×5ラウンドシステム
三重大学教育学部附属中学校
教諭 𠮷水 慶太 先生

1. はじめに
今年度4月から三重大学教育学部附属中学校で勤務しています。世界が1つの大きな課題(新型コロナウイルス感染症)を抱えている現在では、昨日までの常識が今日から通用しないということが起きています。それは英語教育でも同じことが言えます。「英単語をたくさん書いて覚える」「英文法は理解できるまで説明する」「長文を読むときは後ろから日本語に訳していく」など,従来の英語の授業では当たり前だったことが,現在ではクエスチョンということも珍しくありません。(もちろん,良い部分もたくさんあります)1人1台タブレット端末を用いた自動採点テストや授業内チャットなど,授業の仕方も一気に変化しつつあります。

コロナ禍の休業やオンライン授業を経験した生徒にとって,学校で行う対面授業は当たり前ではなく貴重なものであり、学校で行うからには「学校や教室でしかできないこと」を意識して,毎日英語の授業に取り組んでいます。
2. 新教科書

新教科書に目を通したとき,「面白そう!」というのが最初の印象でした。例えば,勤務校で使用しているHere We Go!(光村図書)では,Unit 1からbe動詞,do動詞(一般動詞),法助動詞が出てくるので,これまでの検定教科書を使用していたときと比べて,中1初期に使える表現の幅がとても広くなりました。生徒たちは小学校の英語科や外国語活動で学んだ知識と掛け合わせ,頑張って自分の表現にしていこうとする姿が見られます。しかし,学習内容が増えたのは事実なので,小学校ですでに導入されている表現も含め,既習事項と新出事項をくり返し何度も使うことで定着を図っています。「授業で扱っていない表現は使えない」という従来の制約から解放された今,生徒は自分の言いたいことを授業の中でどんどん言葉にしています。また,このような英語コミュニケーションを重視した授業ではペーパーテストで得点できないという言葉を耳にすることもありますが,「本当の英語力が身につけば,どのようなテストでも良い結果が出せる」と考え,日々の授業に全力を注ぎ,進んでは戻る,行ったり来たりをくり返しています。
一気に増えた新出語句に関しては,生徒と「一度で完璧にインプットする必要はない」という考えを共有しています。その代わりに,授業中に何度も出会う機会を設けています。ここでも行ったり来たりです。ときには授業で扱った語句や文法を生徒がstudent teachersとなり「ドラムを演奏するのはティナだからplayにsをつける」「this morningだから,get upではなくgot upにする」ということを教え合いながら,全員で前に進んでいます。質問が出てすぐに答えられないときもありますが,さらに詳しく調べるきっかけだと,プラスに捉えています。授業中に出てくる「なぜ」を大切にしていくことで,生徒は英語に興味を持ち,集中力を保つことができます。
3. 5ラウンドシステム
5ラウンドシステムとは,教科書を1年間に4〜5回使う横浜市立南高等学校附属中学校のオリジナルカリキュラムです。約2〜3ヶ月の周期で,それぞれ扱う視点を変えながら授業を展開していきます。
しかし,5ラウンドシステムは魔法のメソッドではありません。ただ教科書を5回くり返したからといっても英語力は身につきません。私がこのシステムを部分的に導入しようとした理由は2つあります。それはリスニングと音読をとても大切にしていることと,とんでもない回数をくり返すということです。圧倒的なインプット量を確保し,授業内だけでも生徒は1年間で教科書本文全ページを何十回も音読します。自宅での音読を合わせるとさらに回数が増えます。ほぼ全ページを暗唱している生徒もいます。もちろん,ただ音読するだけでなく,「発音に気をつけて」「教科書の登場人物になりきって」「語順を意識して」「状況・場面をイメージして」とバリエーションを持たせて,Read and Look upやOverlap,穴あきや並び替え,文頭の語句以外はごっそり削ぎ落としたりすることで,音読に飽きない工夫をしています。課題のレベルを少しずつ上げていくことで,生徒は無意識に難しいタスクをこなせるようになっています。また,最終ラウンドは予定していたリテリングをアップデートして,自己表現活動にしていこうという話を生徒としています。教えを守り着実に力をつけてきた生徒たちとともに,次は型を破っていきます。
4. 帯活動
5ラウンドシステムを導入したことで,授業準備の際に最も意識するようになったのが帯活動です。教科書を想像以上にくり返し,その中で学んだ知識や技能を自分の表現として使うことができるようにしていかなければなりません。帯活動にはバリエーションを持たせています。ざっと紹介させていただくと,「1 Minute Talk」「Picture Description」「Retelling」「パンチゲーム」「同時自己添削英作文」「口頭英文法チャレンジ」「Last Sentence Dictation」「Error Correction」「Pattern Practice Pairwork」「じゃれマガ」「Let’s make questions!」「グルグル」などです。どれも単元テストや定期テストに向けて(もしくはそれらの結果を受けて)必要なものを選択し,回数をこなしていきます。

5ラウンドシステムでは,語彙や文法を学習しないと思われがちですが,むしろ「今日は文法」という導入ではなく,教科書本文に出てくる文脈を活かして自然な形で触れていきます。また,毎時間行っている自己表現活動の中で「〇〇と言いたい」という気持ちが出てきたタイミングで学年に関係なく,伝えたいことが伝わる表現を導入します。「知りたい」「伝えたい」と思っているときが一番インプットに適しているので,この積み重ねで表現を増やしていきます。生徒は学んだ表現をすぐに使いたい(ゲームを買ってもらったらすぐにそれで遊びたい気持ちと同じ)はずなので,新たなパートナーと再び同じトピックについて話す機会も欠かせません。
5. Practice Makes Perfect.

“I like cat.” と生徒が表現したとき,すぐに「catsだよ」と訂正するのではなく,“You like cats. Me too.” のように,会話の中で気づきが生まれるように生徒と英語で話をします。また,「洋画を日本語吹き替えで観た」を英語で言いたいけど言えなかった生徒から質問が出たとき,全員で前に進むチャンスだと思いました。
毎授業このような場面では,すぐに答えを伝えるのではなく,全員で考え,使えそうな単語や表現を出し合います。最終的に私のヘルプなしで “I watched an American movie in Japanese.” が完成しました。自分たちで考えて作り出した英文なので,次に別の友人と話すとき,とても嬉しそうに使っていました。このような経験をくり返すことで,「分からないことは悪いことじゃない」「分からなければ素直に質問しよう」という雰囲気になります。私からも「みんなが考えるきっかけを与えてくれてありがとう」と伝えています。
6 おわりに
第20弾に引き続き書かせていただきました。前回,生徒に普段の授業について記事を書いたと話したとき,「読みたい」「面白そう」と興味を持ってくれたことがとても嬉しかったです。授業が自分事になっている証拠です。授業は教師だけでなく,生徒とともに作り上げるということを改めて実感できた瞬間でした。このような機会を与えていただき,ありがとうございました。これからも生徒と一緒に英語教育学習に尽力していきます。